DAIICHI KEIRI SEMINAR 第一経理ゼミナール 今回のテーマ ストレスへの対処法を身に着ける
第一経理ゼミナールとは、
第一経理グループPR委員会メンバーが、
日々お客様と接する中でお聞きした、
お客様が今知りたいこと、気になることをクローズアップ。
解決のための本をお客様に代わって
読み+勉強会を行い、ブックレビューします。
今回のテーマは「ストレスへの対処法を身に着ける」です。どんどん複雑になっていくビジネス環境、人間関係など、ストレスは生きていくうえで避けては通れないもの。耐性がある人もいるけれど、大半はないわけで……と、思っていませんか?
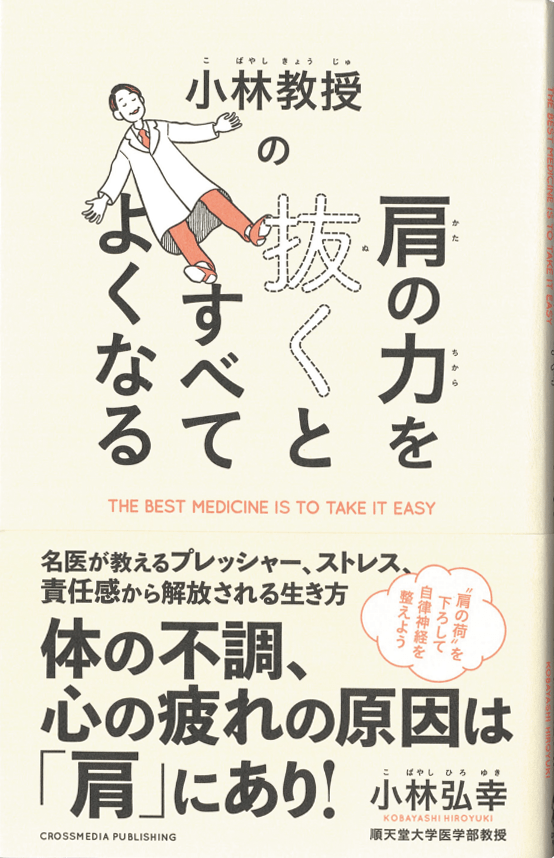
クロスメディア・パブリッシング 1,380円+税)
小林教授の『肩の力を抜くとすべてよくなる』
肩の状態は、心の状態や考え方、感情に直結している!
肩の力を抜いたとき得られる、心と体の健康につい学べる本
「あなたは今、肩に力が入っていませんか?」本書の冒頭で著者の小林弘幸教授はこう問いかけます。私たちは不安を感じると、無意識のうちに肩に力が入ってしまいます。肩に力が入った状態が続くと自律神経が乱れ、さらなる不調を引き起こすといいます。そして、その影響は単なる肩こりなどの身体の不調にとどまらず、実は肩は「心」の持ち方、考え方、感情などと強く結びついていることがわかります。
「力が抜けた生き方こそが、楽しく、健康に生きていくコツではないか」という考えのもと、どうすれば肩の力を抜けるのか、それによって得られる「心の健康」と「体の健康」とはどういうものなのか、不安が心身に与える悪影響のメカニズム、それらを取り除く(軽くする)考え方、自律神経を整える実践法と多岐にわたる1冊です。
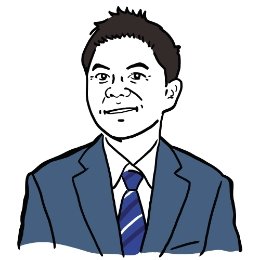
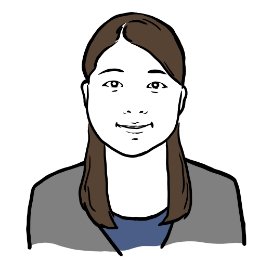


友野さん
坂井さん
荒木さん
いいね!
心の余裕を生むレッスン「恩人リスト」を
実践してみたい!
肩の力を抜く方法がたくさん挙がっていますが、特に印象的だったのは、恩人リストを作ることです。これまでの人生を振り返って、お世話になった人を順番に真っ白い紙にリストアップしていく方法です。感謝の気持ちを伝えることで、心の中に余裕が生まれるそうです。私自身も困難な状況に直面したとき、助けてくれた周りの方々への感謝の気持ちを振り返ることで、前向きになれた経験があるな、と思いました。時間を見つけて実践してみたいです。
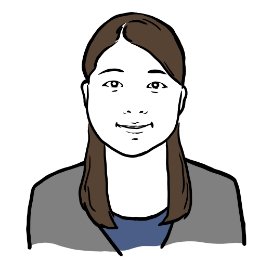
いいね!
自律神経を整えるための
意外な方法が面白い
「古いアルバムの写真を捨てる」「年末のセールで靴をまとめ買いする」「恩人リストを作ってみる」「昔、通っていた中学や高校に行ってみる」など、一見すると自律神経の改善とは関係がなさそうな行動が紹介されています。これがどうして乱れた自律神経を整えるの?と思うかもしれませんが、肩に力が入る具体的なシーンごとの解説や、著者自身の体験談を交えて理由を丁寧に説明しており、とても納得しやすい内容でした。

いいね!
将来への漠然とした不安は「今をないがしろにしている」……
その言葉にハッとしました
「今を大事に生きる」という言葉が何度も出てきて印象的でした。過去にあった嫌なことや、いつ起こるかわからない将来の不安にとらわれている時間は「今をないがしろにしている」ことにほかならない、と気づいてハッとしました。
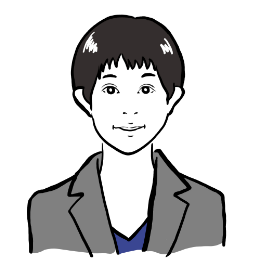
まあまあ。
すぐ実践できるかどうかは……
少し難しいかもです
本を読み進めていると、なるほど!と思うことやそうすればいいんだなということがたくさんありました。ただ、明日から早速実行に移せそうかと考えると、少し難しいように思いました。

まあまあ。
仕事、人間関係に悩める人のための本
それ以外の悩みにはピンとこないかも。
仕事や人間関係で悩みがある方に向けた本なので、悩みのベクトルが違うと、ピンとこないかもしれません。
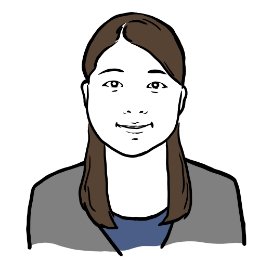
テーマのまとめ
心身の健康や今を生きる知恵、背中を押してくれるポジティブな言葉で前向きになれる本
仕事や学校、家事、育児など、現代社会で懸命に生きる中で、知らず知らずのうちに肩に力が入ってしまっている人にお薦めしたいです。肩の力を抜くための具体的なテクニックが詰まっています。考え方など、健康のために取り組むべきことが多く書かれていますが、その一方で未来の自分のための時間の使い方、ポジティブな考え方など、背中を押してくれるようなことも多く書かれています。この本を読んで前向きな気持ちになっていただけたらと思います。
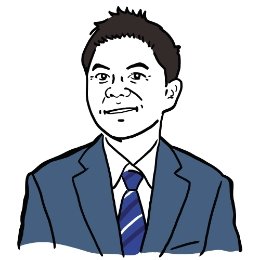

坂井さんまとめ!
今回のひとこと
実は、経営者が「健康経営」について考えるヒントになる一冊です
年齢にかかわらず、抑うつ状態による休職や退職の相談が増えてきていると感じます。パワハラや業務過多などの極端な理由だけではなく、運動不足や不摂生な生活習慣などの日々の積み重ねから自律神経が乱れて抑うつ状態になっている方も少なくないのではないでしょうか。本書の中でも、「働き盛りはほとんど運動していない」という指摘がありました。会社が従業員の運動を促進したり、生活習慣改善の機会を提供したりすることで、結果的に精神的な健康にもつながり、休職による人手不足の予防につながるかもしれません。経営には関係なさそうな本ですが、経営者が「健康経営」を考える上でのひとつのヒントになると思います。
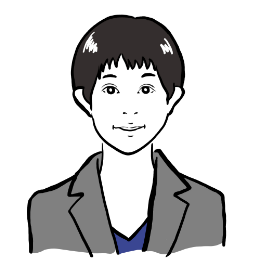
この本の推薦者 大槻さん
いろいろなプレッシャーやストレス、責任感から、肩に力が入りっぱなしになってしまう方は多いと思います。要らないものは捨て、大事なものは守る。深い呼吸をして、自律神経を整えられると、心身の調子が良くなるかもしれません。読みやすい内容なので1日で読めると思います。